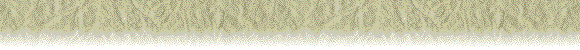 |
|
旧市街の道
旧市街はスヴォルノスティ広場を中心に環状に発展している。 シロカー大通りはカーヨヴィスカー通りと名を変え、それは滑らかにコステルニー通り Kostelni につながり、カプランカ近くでマスナー通り Masna に入り、ラドニチュニー通りを横断するとドロウハー通り Dlouhá となり、シロカー大通りにぶつかり一周する。
放射状の道としては広場から東にホルニー・ブラーナ橋から外部に出るホルニー通り、北にラゼブニツキー橋を経て対岸へ行くラドニチュニー通り、そして南岸に至るカーヨヴィスカー通りがある。
その他シロカー大通りから北へ木橋を渡りプラーシュチョヴィー橋の下をくぐりイェレニー庭園
Jeleni に至る道、そしてラゼブニツキー橋のたもとからホルニー・ブラーナ橋へ至るパルカーン通
Parkán などがある。
北岸の旧市内にはラゼブニツキー橋からラトラーン通りがラトラーンを経てブディヨヴィツェ門まで続き、ラトラーン通りからノヴェー・ミェスト通り
Nové Mesto がエッゲンベルクのビール醸造所まで続いている。
|
|
|
|
チェスキー・ブディヨヴィチェからのバスはバス・ターミナルに着く。 そこから半島状の旧市街へまず行ってみよう。
ヴルタヴァ川沿いの舗装道路に出るとこの地に着いて初めてチェスキー・クルムロフの全景を目の当たりにする。 やがて川側にせり出した見晴台があるが、ここから町を一目見ただけですばらしい所にこれたと感動すること間違いなしだ。
ヴルタヴァ川に沿って右に自動車道と分かれたあたりが旧市街地への入り口で、このあたりにはペンションが何軒かある。 このホルニー通り Horni はすぐにこの半島の最もくびれた部分にかかる石橋、ホルニー・ブラーナ Horní Brána にさしかかる。 ここを渡るとすぐ右に地域博物館 Okresní vlastivedné muzeum がある。 この建物は1650年から1652年の間にイエズス会の神学校として建てられたもので、第二次大戦後博物館としてこの地域の歴史、民俗、工芸等の展示をしている。 博物館の隣は空き地となっており、ヴルタヴァ川の対岸の展望に絶好の場所である。 最初のページの一番上に掲げた写真がここからクルムロフ城を撮ったものである。
右写真はホルニー通りで、聖ヴィート教会の前に建つカプランカ Kaplanka と呼ばれる1514年から1420年にかけて助祭司祭のために建てられた家の前から振り返る形で撮ったものである。 中央の建物が後述のホテル・ルージェだ。
|
|
博物館の向い側の大きな建物がホテル・ルージェ Hotel Ruze だ。 この建物は大きく2つに分かれていて、1つは1586年から1590年の間にロジェムベルク家のヴィルヘルムによって建てられ、イエズス会寄宿舎として寄進されたもであり、もう一つは肉屋のタンクル家の住居だったものを1590年にヴィルヘルムの意向で市が買い取り、イエズス会に寄進した建物からなる。 1613年にイエズス会は後者の地を舞台変換のための木製設備を備えた劇場とし、教育のために使い始めた。 前者は改装され1889年にホテルとして開業し、後者はその後町の劇場として使われていたのを1980年代に閉鎖し、その後改装され現在ホテルの一部となっている。 ホテル・ルージェはこの町一番の71室を誇る5つ星ホテルで、1999年5月に大幅な修復が行われた。 ホルニー通り側から、しかも近くから見ると長い白壁にいくつかの小さな入り口があるだけで全くぱっとしない。 ヴルタヴァ川の対岸に行って見ると何と上の写真のようにすばらしい外観をしているのに驚かされる。
|
|
ホテル・ルージェの隣のカプランカの脇の奥まった所にある石段を少し登ったところが教区教会の聖ヴィート教会である。 この町で目立つ建物と言えばクルムロフ城とその城塔を除けば何といってもこの聖ヴィート教会なのだが、このホルニー通りからだとよく見えない。 クルムロフ城とその城塔から見たこの教会の写真はそのページで紹介するので、ヴルタヴァ川の南岸から撮った写真をここでは左に掲げておこう。 教会の右側がホテル・ルージェだ。
このゴシック様式の教会はアルデンベルクのリンハルト Linhard of Ardenberg
の設計により1407年に建設が開始され、1439年に奉納されている。 1593年から1597年にはロジェムベルク家のヴィルヘルムとその3人目の妻アンナ・マリーの碑銘付の墓など、内装が充実された。
主祭壇にはこの教会の守護聖人である聖ヴィートとマリアが描かれており、左の側廊北側にはヤン・ネポムツキーの礼拝堂
kaple sv. Jana Nepomuckého があり、ここには1729年のピエトロ・ファン・ロイ
Pietro van Roy の「聖ヤンの死」が見られる。
|
|
ホルニー通りの突き当りがこのスヴォルノスティ広場 Námesti Svornosti
だ。ここはチェスキー・クルムロフ旧市街地最大の広場で、この半島部のほぼ中央に位置する。 下写真は広場南側で、左に見えるマリア記念柱
Maríanský sloup はペストに対する庇護を願って聖母マリアにささげられたものである。 そのマリア像はプラハの彫刻家マトゥーシュ・ヴァーツラフ・イェッケル
Matyás Václav Jãckel 等によって1712年から1716年に製作された。
広場北側の壮麗な建物は16世紀にルネッサンス様式で建てられた市庁舎。 その右にインフォメーションがある。 この市庁舎の左側には鐘がつるされているが、これは市評議員を招集するためのもので、後には火災を知らせるために使われた。
|

スヴォルノスティ広場の西側2本目の道がシロカー・ウリツェ Siroká
ulice、シロカー大通りである。 この道はかつてこの町で最も幅の広い道だったので大通りと呼ばれるようになった。
右の写真ではひっそりとしているが、観光シーズンには露店が並びにぎわうと言う。
写真中央の白い建物は20世紀半ばに第2次世界大戦のために製造を停止したビール工場跡であり、修復され現在エゴン・シーレ国際文化センター
Egon Schiele Art Center として彼の作品や資料の展示の他、各種文化的催しに使用されている。 エゴン・シーレ
Egon Schiele は20世紀初頭のウィーンの絵画の巨匠で、彼の母がこの地の出身だったことからか、第1次大戦前にこの地を訪れ絵画を描いている。
この道を北(写真の手前方向)に進むと左側にかつて町の武器庫だった建物があり、さらに進むとオストロフ
Ostrov = 島と呼ばれる所に着く。 この先は狭い木橋でヴルタヴァ川を渡り、城とロココ劇場および庭園を結ぶ陸橋プラーシュチョヴィー橋に至る。
|
|
右写真はオストロフ広場 Nam Ostrov から眺めた上層の城の荒々しい壁。 天然の岩盤の上にヴルタヴァ川の川面からそそり立つように聳える様がよくわかる。
下の写真はオストロフのたもとの橋(下写真に見られる。)を渡った対岸から撮影したもの。 白い塔から右側がシロカー大通りの裏側すなわちヴルタヴァ川側の景観。 オストロフは白い建物の向こう(東)側に当る。 ヴルタヴァ川にはここに堰が設けられており、ここから先は多少水位が低くなっている。
上層の城館と右端に見える城の塔との距離がかなりあることがよくわかるだろう。 このことから城の規模が推測できるだろう。 城館の左側に白い幅の狭い建物が見えるが、これがプラーシュチョヴィー橋だ。
 |
|
シロカー大通りを南に向かうと、途中からカーヨヴィスカー通り Kájovská
と名前を変え、やがて三叉路で大きく右に曲がる。 このあたりはスヴォルノスティ広場のすぐ南側にあたる。 そのままカーヨヴィスカー通りを右に曲がるとやがて立派な石橋
most dr. E. Benese に至る。 下の写真はその橋の上から下流(西方)を望んだものだ。
 橋のたもとを右折するとそこはこの町でも最も古い道の1つと言われるリバージュスカー通り Rybárskà で、漁師町という意味のようだ。 この道はヴルタヴァ川に沿ってプラーシュチョヴィー橋およびオストロフ広場に渡る狭い橋のところまで続いている。 橋のたもとを右折するとそこはこの町でも最も古い道の1つと言われるリバージュスカー通り Rybárskà で、漁師町という意味のようだ。 この道はヴルタヴァ川に沿ってプラーシュチョヴィー橋およびオストロフ広場に渡る狭い橋のところまで続いている。
石橋を渡ったところをヴルタヴァ川に沿って反対の左側に行くと上に掲げた聖ヴィート教会やホテル・ルージェの写真を撮った眺めの良い場所を経て木立に囲まれた公園
Mestské Sady に至る。 この公園の手前にはかつてイエズス会の夏の宿舎であった建物が、現在ホテル・ゴールド
Hotel Gold として営業している。
この南岸からの眺めはなかなか良いので、時間が許せばぜひ訪れてることを薦める。
|
|
スヴォルノスティ広場の北端を北にラドニチュニー通り Radnicni を行くとラゼブニツキー橋
Lazebnický という立派な木橋を経て北側の市内へ通ずる。 チェスキー・クルムロフ城へいく場合、そしてラトラーンを経てブディヨヴィツェ門へ行くときはこの道を通る。
ここではブディヨヴィツェ門近くのバス停(右写真)を基点としてラゼブニツキー橋の方へ向かうことにする。 ブディヨヴィツェ門から続く道はかなり高い位置を通っており、チェスキー・ブディヨヴィツェからの自動車道はその下をくぐっている。 バス停からはまずその上の道に登る。 ヴルタヴァ川を渡ったところがブディヨヴィツェ門(下写真)だ。 チェスキー・クルム ロフにはかつて10の市門があったが、現在残っているのはここだけだ。 この門は1598年から1602年にかけて建造されたもので、その10の門の中で最後に作られたものだ。 ロフにはかつて10の市門があったが、現在残っているのはここだけだ。 この門は1598年から1602年にかけて建造されたもので、その10の門の中で最後に作られたものだ。
門から続くラトラーン通りがY字型に分岐するあたりがこの通りの名前のもとになったラトラーンという地域だ。 このあたりは城の臣下や職人たちが住居を構えていた。
ラトラーン通りはやがて門のようなもの(下写真)をくぐり、チェスキー・クルムロフ城の中央門、チェルヴェナー・ブラーナ
Cervená Brána = 赤い門の前に出る。 この門のようなものは実は門ではなく、城館からこのラトラーン通りの上を渡る回廊である。
チェルヴェナー・ブラーナをさらに少し先に行った所を左に折れると1350年に創設されたかつてのフランシスコ派の修道院
byv. Minoritský kláster があり、その前がトラミーン Tramin
と言う公園だ。
 ラトラーン通りのこのあたりがチェスキー・クルムロフの商業地域だ。 なかなかセンスのある外観を持った高級店や趣向を凝らして客をひきつける店がこの道に沿ってちりばめられている。 そのいくつかを下に掲げておこう。 ラトラーン通りのこのあたりがチェスキー・クルムロフの商業地域だ。 なかなかセンスのある外観を持った高級店や趣向を凝らして客をひきつける店がこの道に沿ってちりばめられている。 そのいくつかを下に掲げておこう。
ノヴェー・ミェスト通りに分岐するあたりからラゼブニツキー橋方面を眺めたものが最後の写真だ。 教会のような建物はかつての聖ヨシュト教会
býv. kostel sv. Josta。 この教会は14世紀前後の創建と言われるが、その後教会の尖塔を保存すると言う条件で市民に売り渡され、病院を経て現在住居となっている。
ラゼブニツキー橋のたもとの建物は床屋として使われていたものだ。 当時の床屋は散髪や髭剃りばかりでなく、歯を抜くことなどが知られているが、ここでは瀉血を行ったり入浴もできたそうだ。 ちなみにこの橋の名は床屋と言う意味だそうだ。
|
|
|
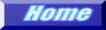  |
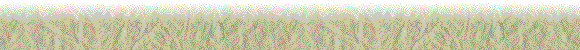 |
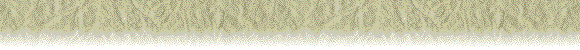

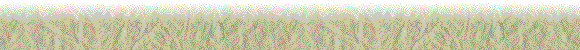






 橋のたもとを右折するとそこはこの町でも最も古い道の1つと言われるリバージュスカー通り Rybárskà で、漁師町という意味のようだ。 この道はヴルタヴァ川に沿ってプラーシュチョヴィー橋およびオストロフ広場に渡る狭い橋のところまで続いている。
橋のたもとを右折するとそこはこの町でも最も古い道の1つと言われるリバージュスカー通り Rybárskà で、漁師町という意味のようだ。 この道はヴルタヴァ川に沿ってプラーシュチョヴィー橋およびオストロフ広場に渡る狭い橋のところまで続いている。  ヴルタヴァ川北岸の市街地
ヴルタヴァ川北岸の市街地 ロフにはかつて10の市門があったが、現在残っているのはここだけだ。 この門は1598年から1602年にかけて建造されたもので、その10の門の中で最後に作られたものだ。
ロフにはかつて10の市門があったが、現在残っているのはここだけだ。 この門は1598年から1602年にかけて建造されたもので、その10の門の中で最後に作られたものだ。 ラトラーン通りのこのあたりがチェスキー・クルムロフの商業地域だ。 なかなかセンスのある外観を持った高級店や趣向を凝らして客をひきつける店がこの道に沿ってちりばめられている。 そのいくつかを下に掲げておこう。
ラトラーン通りのこのあたりがチェスキー・クルムロフの商業地域だ。 なかなかセンスのある外観を持った高級店や趣向を凝らして客をひきつける店がこの道に沿ってちりばめられている。 そのいくつかを下に掲げておこう。



